
葬祭展で出展されていた株式会社ルシェル様...
先日の終活フェア葬祭展では、株式会社ルシェルの代表の方も出展されており、互いにブースを出す中で知り合いました。...
- 2023.10.31
朝晩の空気がひんやりとし、本格的な秋の訪れを感じる今日この頃です。この気温の変化は、私たちに衣替えの季節の到来を告げています。厚手の上着やコートを引っ張り出し、鮮やかな色で私たちを楽しませてくれた夏物を丁寧にしまう時期となりました。
この衣替えの時期は毎年恒例の行事であると同時に、多くの方が「今年も服が多くて片付かない」「どこから手を付けていいか分からない」と、クローゼットの前でため息をつく瞬間でもあります。増え続けるモノに圧倒され、整理を先延ばしにしてしまう…そんな経験は誰にでもあるのではないでしょうか。
しかし、立ち止まって考えてみてください。この衣替えのタイミングは単に服を入れ替える作業ではありません。これは実は、“片付けのチャンス”であり、さらに一歩踏み込んで言えば「ミニ生前整理」を始める絶好のきっかけにもなるのです。

「生前整理」という言葉を聞くと、どのようなイメージをお持ちでしょうか?多くの方は、「終活」の一部や、「人生の最終段階で家族のために行う大掛かりな作業」といった、やや重々しいイメージを持つかもしれません。
ですが本来の生前整理が持つ意味合いは、もっと前向きで日常的なものです。それは、「これからの暮らしを、より快適に、より心地よくするための整理整頓」を意味します。つまり、年齢やライフステージに関係なく、「今」をより充実させ、心地よく暮らすための具体的な方法論なのです。
とはいえ、いきなり「よし、今日から家中の整理を始めるぞ!」と意気込んでも、そのハードルの高さから途中で挫折してしまいがちです。膨大なモノを前に何から手をつけていいか分からず、結局何も進まないまま時間だけが過ぎていく…というケースは珍しくありません。
そこでおすすめしたいのが「ミニ生前整理」という考え方です。
ミニ生前整理とは、文字通り範囲を小さく、区切って、少しずつ進めていくスタイルです。全体を一気にやろうとせず、あえて小さな単位で区切ることで、精神的な負担を減らし、達成感を得やすくします。
たとえば、次のような区切り方はいかがでしょうか。
この季節の衣替えは、まさにこのミニ生前整理を始めるのに最適です。夏物をしまい、冬物を出すという作業の中で自然とすべての衣類に触れることになります。この機会に、「着る服」と「着ない服」を冷静に仕分けし、“自分に本当に必要なモノ”は何なのか、という視点で見直すきっかけが生まれるのです。
衣替えの作業と同時にできる具体的な「ミニ生前整理」の進め方をわかりやすい3つのステップでご紹介します。この手順を踏むことで、クローゼットがスッキリするだけでなく、心にも新しい余裕が生まれることを実感できるはずです。
クローゼットの奥を整理していると「いつか着るかも」「まだ着られるはず」という思いで、何年も仕舞い込まれていた服が必ずと言っていいほど出てきます。過去の自分にとって必要だった服かもしれません。
けれども、整理収納の世界では「1年(一シーズン)着なかった服は、次の年も着ない可能性が非常に高い」と言われています。たとえ流行が巡ってきたとしても自分の体型や好みが変化しているため、結局は袖を通さないままになってしまうことがほとんどです。
「もう少し痩せたら着よう」「高かったから、捨てるのはもったいない」といった感情が、手放すことを妨げる大きな壁となります。しかし、これらの服は結局タンスの肥やしとなり、今本当に着たい服の居場所を奪っている状態なのです。
思い切って手放す決断をすることで、収納スペースに物理的なゆとりが生まれます。このゆとりは湿気やカビを防ぎ、冬物のニットやコートを長持ちさせる効果もあります。そして何より服選びの時間が短縮され、日々の暮らしがスムーズになります。
手放すことへの罪悪感を持つ必要はありません。状態の良い服は、リサイクルショップに持ち込んだり、必要な人へ寄付したり、フリマアプリで次の使い手を見つけたりと、「誰かに活かしてもらう」という前向きな行為に繋げることができます。「もったいない」という過去への執着を手放し、「未来を快適にするため」という気持ちで整理を進めていきましょう。
衣類の中には、単なる消耗品ではない、特別な意味を持つものが存在します。たとえば、お子様の初めての発表会で着用した衣装、人生の大きな節目となった旅行先で購入した服、あるいは家族から譲り受けた大切な一着など、手に取るたびに過去の記憶や感情が鮮やかに蘇る「思い出の品」です。
しかし、思い出を大切にすることと、モノをすべて残すことはイコールではありません。思い出は、必ずしも“モノ”という形の中に限定して存在するわけではないのです。
大切なのは、「その服がなくても、思い出を大切にし続けられるか」という視点を持つことです。たとえば、服全体ではなく、生地の一部を切り取って小さなポーチにリメイクする、着用している姿を写真に撮って記録に残す、当時の気持ちやエピソードを日記やデジタルデータに書き留めて「形ではなく記憶で残す」という方法があります。
また、思い出の品をすべて残したい場合は、「思い出の服はボックス1つ分だけ」「それぞれのイベントから最も心に残る1つだけを残す」など、具体的なルールを決めておくと、気持ちの整理がつきやすくなります。
このステップの核心は、「なぜこれを残したいのか」という“残す理由”を明確にしていくことです。理由を言語化することで本当に大切にすべきもの、自分の人生にとって価値のあるものが見えてきます。そして、それ以外の「何となく」で残していたモノを感謝とともに手放す準備ができるのです。

整理整頓というと、「いかに効率よく、きれいにたくさんのモノを詰め込むか」という「収納テクニック」に意識が向きがちです。しかし、ミニ生前整理の仕上げとして最も大事なのは、「空きスペースを意識的に残す」ということです。
衣類をぎゅうぎゅうに詰め込まず、ゆとりある収納を確保することは、そのまま暮らしの余白につながります。物理的なゆとりは心理的な余裕を生み出します。「また何か新しいもの(服に限らず、新しい経験や習慣なども含めて)を迎え入れられる」という心の余裕が、暮らしを軽やかにしてくれます。
さらに実用的なメリットもあります。服を詰め込みすぎないことで、クローゼット内の通気性が格段に良くなり、湿気がこもりにくくなります。これは、カビの発生や不快なニオイの予防にも非常に効果的です。特にデリケートな冬物のニットやウール、カシミヤのコートなどは、良い状態で長持ちさせることができます。
理想的なのは、収納スペースの7〜8割程度にモノを収め、2〜3割の空きを作ることです。この「余白」こそがミニ生前整理がもたらす最大の快適さであり、あなたの暮らしの質を高めるための重要な要素となります。
整理整頓、特にミニ生前整理がもたらす効果は、単に部屋がきれいになる、服が選びやすくなる、といった現在の快適さだけに留まりません。実はこの行動は、自身の未来の安心を築くための非常に重要な一歩となるのです。
家の中が整理され、モノが適正な量に保たれていると、予期せぬトラブルを防ぐことができます。たとえば、モノが多い状態では掃除がしにくく、どうしてもホコリが溜まりやすくなります。冬場は暖房器具の使用が増える季節ですが、近くにホコリや衣類が山積みになっていると小さな火種が大きな火災に繋がるリスクを高めてしまいます。整理は、安全対策の一環でもあるのです。
また、家の中のモノの場所が把握できているという状態は、あなた自身が健康でいる間だけでなく、もしもの時に大きな安心をもたらします。
もし、あなたが体調を崩して寝込んでしまった時、あるいは予期せず入院することになった時、家族は「どこに何があるか」を把握できず、困惑してしまうでしょう。医療関係の書類、保険証、普段使っている日用品のストック…それらがすぐに取り出せる状態になっていれば、家族の負担は大きく軽減されます。
つまり、日々の「ミニ生前整理」は、今の暮らしを快適にするだけでなく、将来、自分や家族を助けるという側面を持っているのです。
遺品整理の現場では、「もっと元気なうちに、少しずつでも整理しておけばよかった」「母の思い出の品が多すぎて、何が大切なのか分からない」といった後悔や苦悩の声がよく聞かれます。そのような未来を避けるためにも、まだ体力があり、判断能力がしっかりしている今から、衣替えをきっかけに少しずつ取り組んでいくことが何よりも大切なのです。

ミニ生前整理を成功させ、それを習慣にするための一番のコツは、「完璧を目指さないこと」です。最初から全てを一度に片付けようとすると、途中で疲弊し、結局また元の散らかった状態に戻ってしまいがちです。
忙しい毎日の中でも、負担なく続けられるように、「1日5分だけ」を目安にすることを強くおすすめします。
たった5分であれば、毎日の生活の中に無理なく組み込むことができます。たとえば、朝起きてすぐ、あるいは夜寝る前のわずかな時間で十分です。
このように、アクションを小さく区切ることで、「今日はここまでやった!」という小さな達成感を毎日積み重ねることができます。この達成感が、片付けを特別な作業ではなく、歯磨きや洗顔と同じように自然と日常の一部へと変えていきます。
また、片付けが終わったら、必ず「よくやった!」「今日も5分続けられた」と、自分自身をほめることも大切です。心理的な報酬を与えることで、習慣化はより定着しやすくなります。
さらに、家族がいる場合は、「1日1捨てチャレンジ」のように、ゲーム感覚で楽しみながら取り組むのもおすすめです。大切なのは、モノを減らすこと自体を目的とするのではなく、気持ちよく、安全に暮らせる空間をつくることを意識することです。
寒くなってくると私たちは暖かい部屋から出るのが億劫になり、行動力が鈍りがちです。だからこそまだ体が動きやすいこの秋の季節は、片付けを始めるベストタイミングと言えます。
衣替えというきっかけを利用して、少しずつ服の整理を進めておくことで、年末にやってくる大掃除の負担もぐっとラクになります。計画的な行動は、未来の自分を助けることに繋がるのです。
“ミニ生前整理”は繰り返しますが、決して大げさな「終活」ではありません。それは「今を快適に、より前向きに暮らすための整理」です。
モノを通じて自分の持ち物や暮らし方を見つめ直すことは、自分自身の価値観を再確認する作業でもあります。そしてこの整理が完了した時、物理的な空間だけでなく心にも新しい余裕が生まれていることに気づくでしょう。心にゆとりが生まれれば、家族や友人との時間もより穏やかに、豊かになります。
この秋はぜひ、衣替えのついでに“未来の自分”のためのミニ生前整理を始めてみませんか?数年後には、きっと「あの時、やっておいてよかった」と心から思えるはずです。

 この記事の筆者
この記事の筆者

先日の終活フェア葬祭展では、株式会社ルシェルの代表の方も出展されており、互いにブースを出す中で知り合いました。...

ご遺族で遺品整理をする場合 遺品整理をご遺族がする場合、まずは分別からスタートしましょう。故人が病気などで長期...

一度書いた遺言書を取消可能??その方法について 結論からいいますと、1回作成した遺言書を取り消すことはできます...

人生が残り少なくなってきたとき、初めて感じる不安や死に対する恐怖、残された家族への想いなどを実感するようになっ...

大阪府交野市の団地で家財整理をさせていただきました。 物でいっぱいだったお部屋の整理しながら運び...
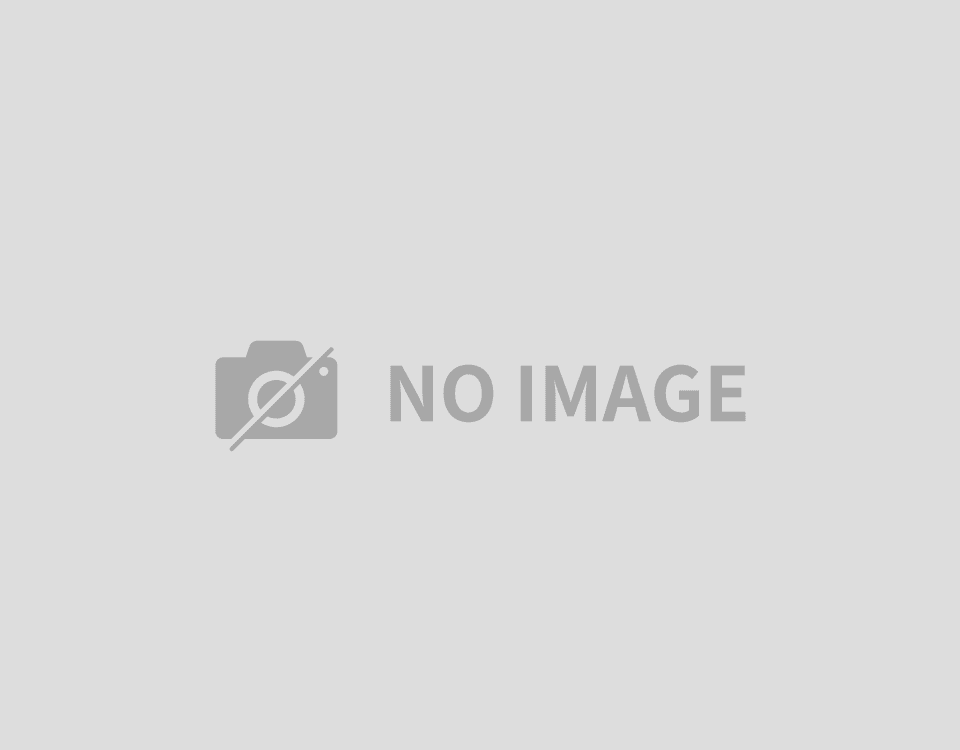
遺品整理、生前整理、特殊清掃の場合、部屋の広さや処分品の量により価格が異なります。 見積もりは無料ですので、ま...