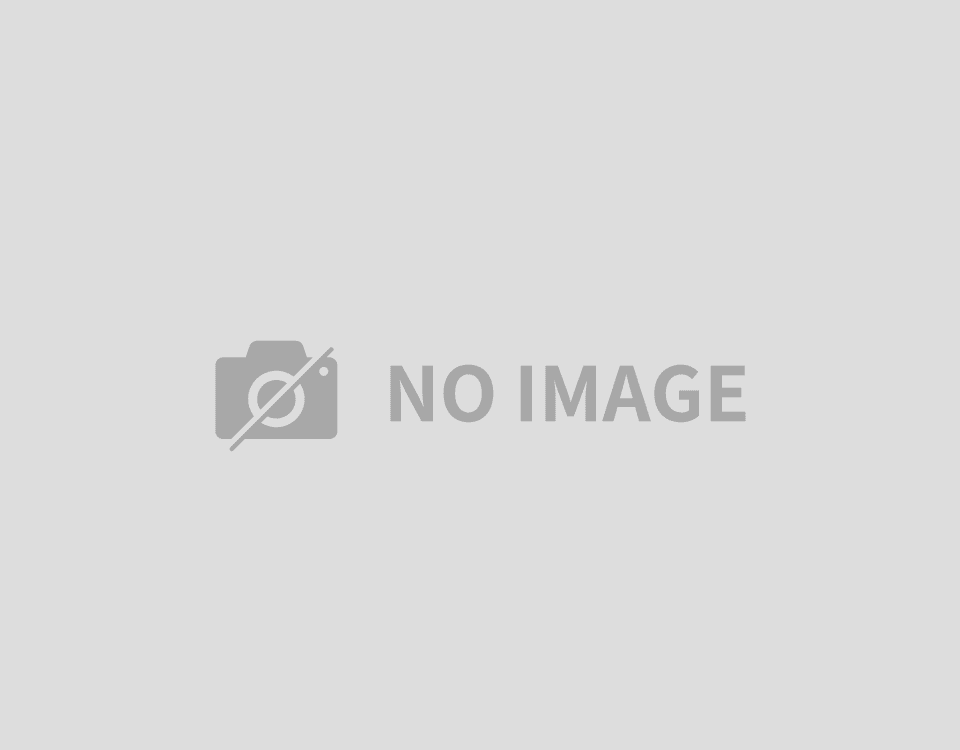
法事と法要 お参り...
●「法事」とは、葬儀や年忌法要等の弔事の行事や仏前結婚式・除夜会・元旦会・はなまつり等の仏事のことを言います。...
- 遺品整理
- 2016.05.25
実家を離れて暮らしていると、
「最近、電話しても元気がないな」 「前に帰省した時よりも、
特に一人暮らしの親御さんを持つ方にとって、健康面だけでなく生活環境に対する不安は尽きないものです。
そして、その不安の一つが「物の多さ」ではないでしょうか。
片付けが進まず物が散乱している状態は、
しかし、親に生前整理の話を切り出すのは簡単ではありません。
この記事では生前整理の提案に悩む方が、

生前整理と聞くと、「まだ元気なのに縁起でもない」「
一言でいうと、生前整理とは「自分自身の意思で、
一方、遺品整理は、故人が亡くなった後に残された遺族が行う整理
この二つには、決定的な違いがあります。
遺品整理では、
しかし、生前整理は、まだ元気なうちに自分自身で「必要な物」
また、生前整理の目的は、
つまり、生前整理は「未来への準備」であり、ご家族にとっても親御さんご自身にとっても、
生前整理が良いことだとわかっていても、いざ親に話すとなるとためらってしまうものです。それは、
こうしたデリケートな問題だからこそ、

親御さんが「それならやってみようかな」
「なんでこんなに物があるの?」「
代わりに、「一緒に片付けようか」「手伝おうか?」と、
片付けは「捨てる」ことだけではありません。
親御さんが「これは残しておきたい」と言ったら「そうだね、
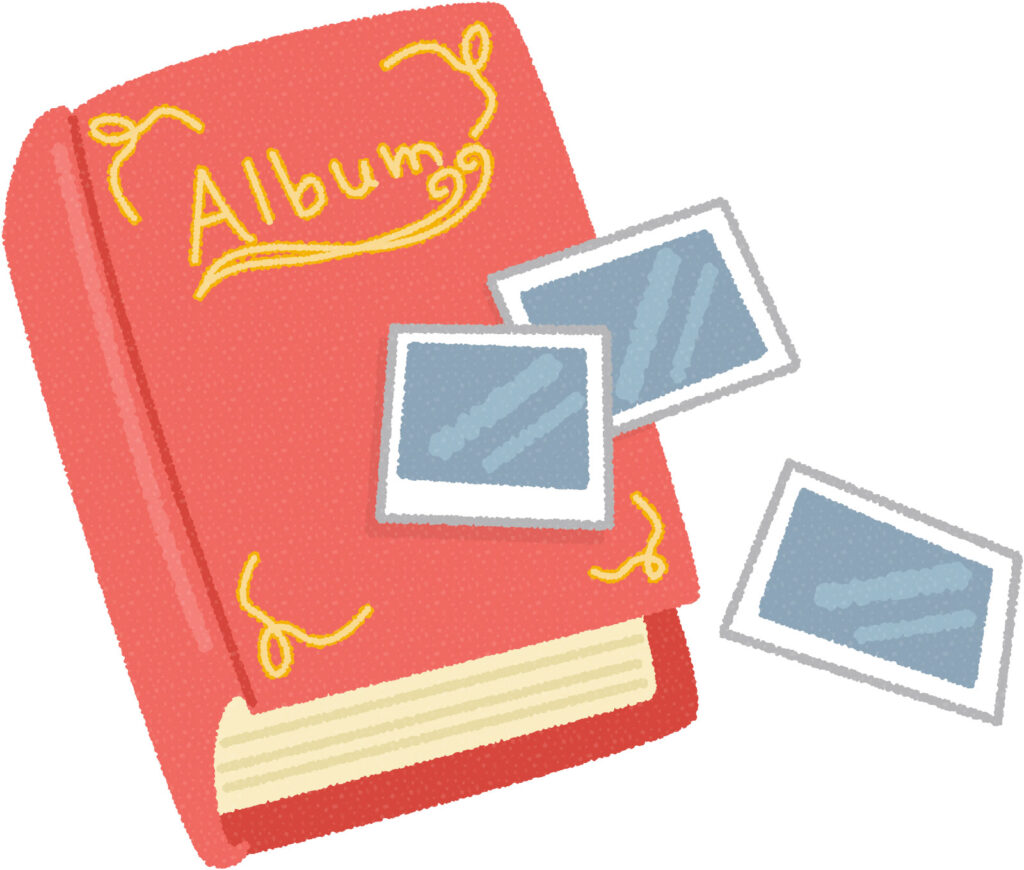
親御さんにだけ「片付けなよ」と言うのではなく、「最近、
このアプローチは、「自分だけではない」という安心感を与え、
抽象的な「安心」だけでなく、親御さんが「確かに、
特に、「安心」という言葉は、
「思い出の写真は捨てられない」と抵抗する親御さんには、「
物理的なスペースは減らせますが、思い出は手元に残るため、
いざ生前整理を始めると決めたら、
いきなり家全体を片付けようとすると、
小さな成功体験が、次のモチベーションにつながります。
片付けの時間は、単なる作業ではなく、
親御さんは、自分の人生が子に認められ、
一緒に仕分け作業を行うことで、「これは残す」「これは譲る」
譲る相手が見つからない場合は、「
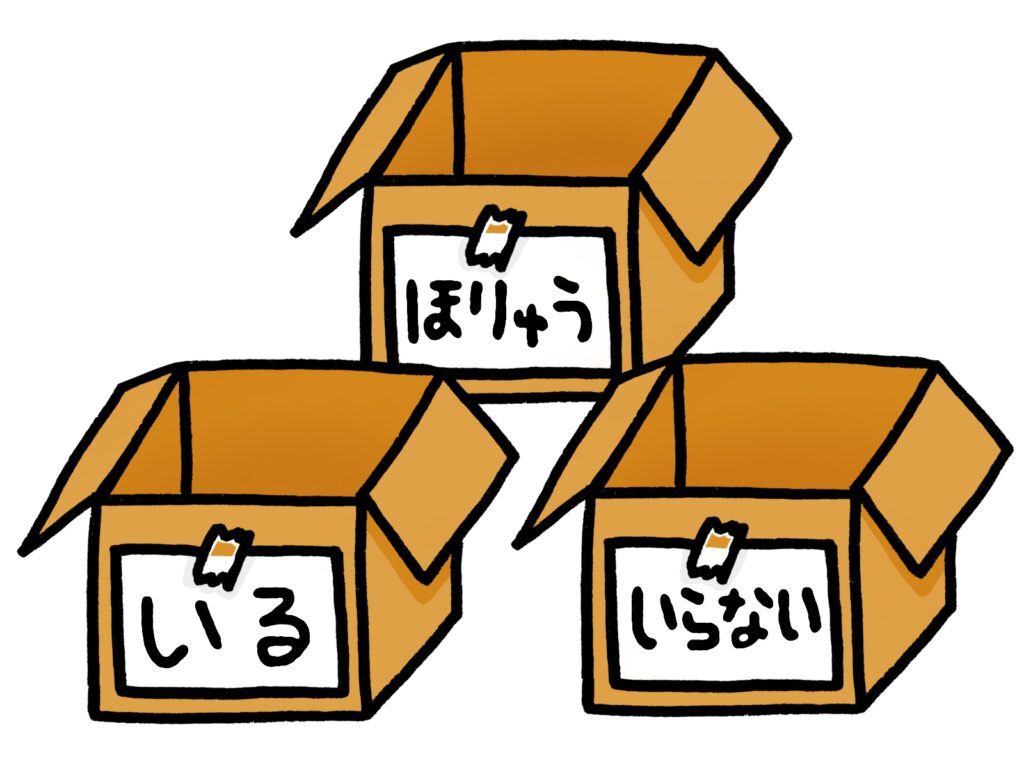
自分たちだけで全てをやるのが難しいと感じたら、
第三者であるプロの力を借りることで、
特に最初のうちは、少しずつ進めることが大切です。
生前整理の際には、以下の情報をまとめてもらうと、
一度生前整理が終わっても、また物は増えていくものです。
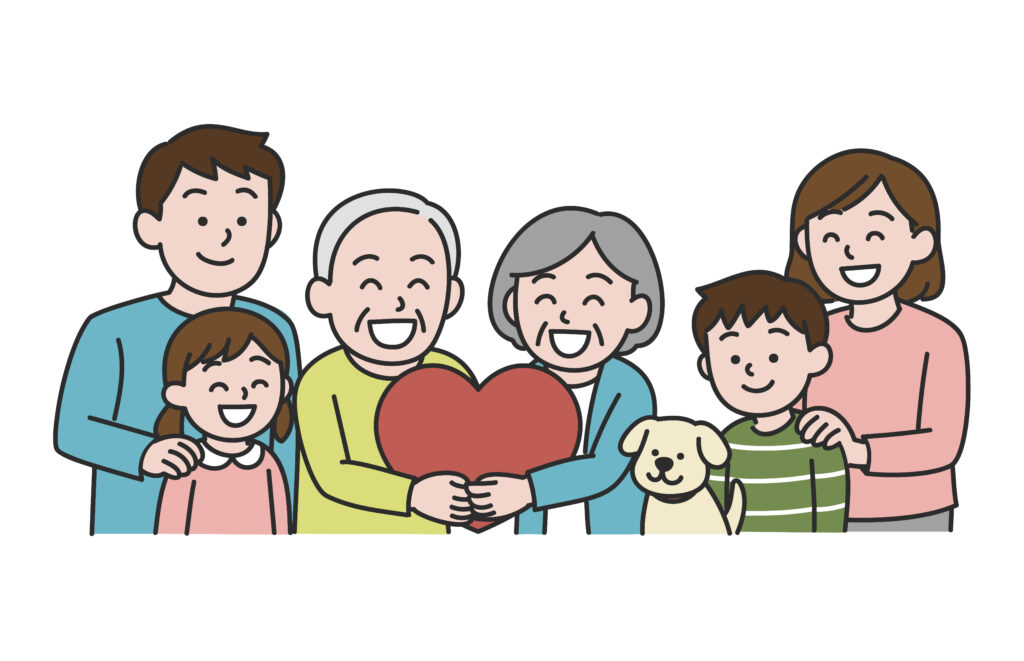
生前整理は、単なる物の片付けではありません。
それは親御さんの人生を肯定し、感謝を伝える時間であり、
この記事を読んでくださった皆さんが、
親子の未来をより明るくするための第一歩、
 この記事の筆者
この記事の筆者
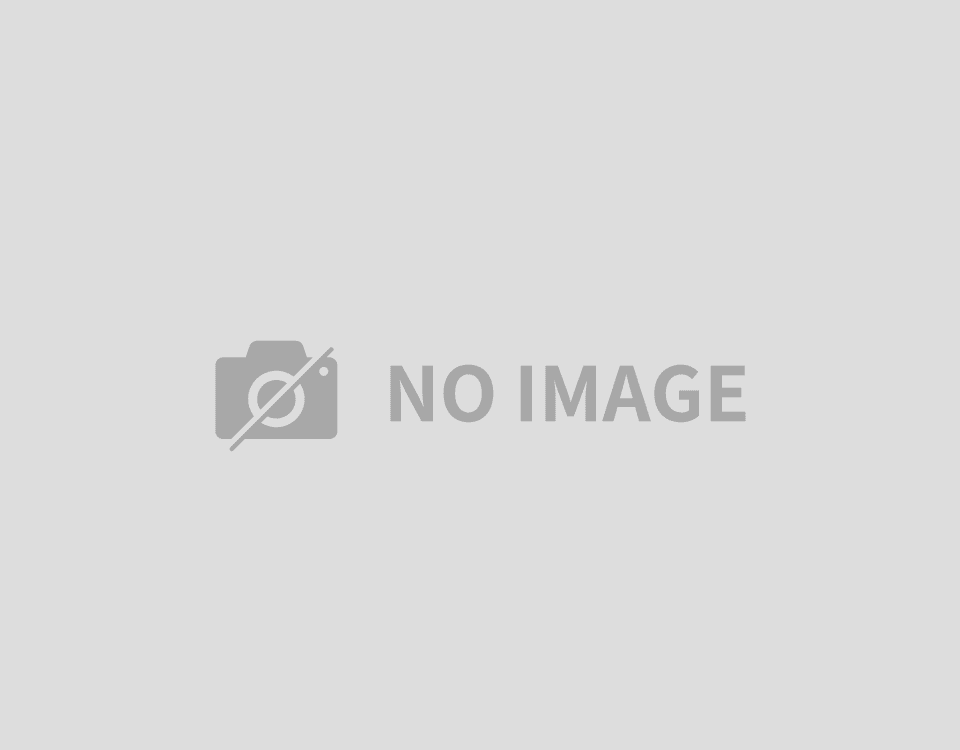
●「法事」とは、葬儀や年忌法要等の弔事の行事や仏前結婚式・除夜会・元旦会・はなまつり等の仏事のことを言います。...

自分の最期を考えてみましょう 最近では超高齢化社会となってきたと共に、医療や情報の発達も加速しているため、元気...

終活はいつから始めるの?準備開始のポイントについて 残される家族に迷惑をかけないように、終活をしておきたい。 ...

今日は大阪は夏のような暑さでした。 成年後見人の司法書士の方のご依頼で、大阪市城東区で生前整理をさせていただき...

書類や服が散乱してる部屋から、重要書類を探しながら作業させて頂きました。 無事、書類も見つかり2日間で作業完了...

故人と親交のあった人たちに遺品をわけあうことを「形見分け」といいます。現在は、「形見整理」で世間に知れ渡ってい...